イギリスの地名には、英語っぽくないどこか独特な響きがありますよね。
エディンバラやカンタベリーといった”〜バラ”、”〜ベリー”といった地名がイギリスにはたくさん存在していますが、これらを英語で表記すると「burgh(brough、boroughとなる場所もある)」、「bury」となり、英語とは思えないつづりや音になっています。
そして、このバラやベリーの語源は同じだとされていますが、いったいどのような意味があるのでしょうか?
また、なぜバラとベリーに分かれているのでしょうか?
今回はエディンバラやカンタベリーの由来を語源の視点から解説していきます!
〜バラ・〜ベリーは「お城」や「砦」を意味する⁉︎

〜バラ・〜ベリーの語源
エディンバラやカンタベリーの他にも、フレイザーバラ(Fraserburgh)やニューベリー(Newbury)のようにイギリスには〜バラや〜ベリーがつく地名がたくさんありますが、これらはいったいどのような意味があるのでしょうか?
まずは、〜バラと〜ベリーの英語表記をそれぞれ見ていきましょう。
〜バラは「brough、burgh、borough」、〜ベリーは「bury」と表記されます。
これらはゲルマン語由来の古英語「要塞化された町、砦に囲まれた町」という意味のburg、burhが語源であるとされています。
このburg、burhと同じように〜バラと〜ベリーは「城、砦」という意味があり、この言葉が徐々に変変化していき、イギリスの北部では「brough、burgh、borough」に、イギリスの南部では「bury」に変化していったといわれています。
エディンバラなどバラがつく地域はスコットランドに多く、カンタベリーなどベリーがつく地域はイギリス南部に多くみられます。
イギリスの地図を見てみるとより分かりやすいので、興味がある方はぜひ地図で確認してみてください。
エディンバラの由来
先ほどの説明で〜バラ(brough、burgh、borough)は「お城、砦」という意味があると述べましたが、エディンバラ(Edinburgh)はどのような意味があるのでしょうか?
実は、エディンバラのエディンは「Eidyn」という丘の名前で、お城・砦を意味するバラ(burgh)と合わさって「エディンの丘の砦」という意味になります。
またこの他に、エドウィン王の名前にちなんで「Edwin’s burgh」と名付けられ、それが変化して「Edinburgh」になったという説があります。
カンタベリーの由来
ベリー(bury)についても同様、「お城・砦」という意味があると説明しましたが、カンタベリー(Canterbury)にはどのような意味があるのでしょうか?
エディンバラと同じようにカンタベリーもカンタ(Canter)とベリー(bury)に分けられていますが、カンタ(Canter)はケント人という意味があり、「お城・砦」を意味するベリーと合わさって「ケント人の砦」という意味になります。
ドイツ語との関係
先ほどバラやベリーはゲルマン語が由来と述べましたが、同じゲルマン系であるドイツ語にburg「城、城塞」という言葉があります。
例えば、現在のドイツにもフライブルクやハンブルクなどburgがつく地名がたくさんありますが、これらはバラやベリーと同じく「城、砦」という意味があります。
この点からも〜バラや〜ベリーがドイツ語と同じゲルマン語が由来であることが分かりますが、ここである疑問が生まれます。
実は、イギリスにはバラやベリーの他にも城や砦を意味するチェスターがつく地名がたくさん存在しています。(例:マンチェスターなど)
なぜバラやベリーの他に同じ意味「お城・砦」を意味する地名「チェスター」が存在しているのでしょうか?
なぜチェスターとバラ・ベリーが混在している?
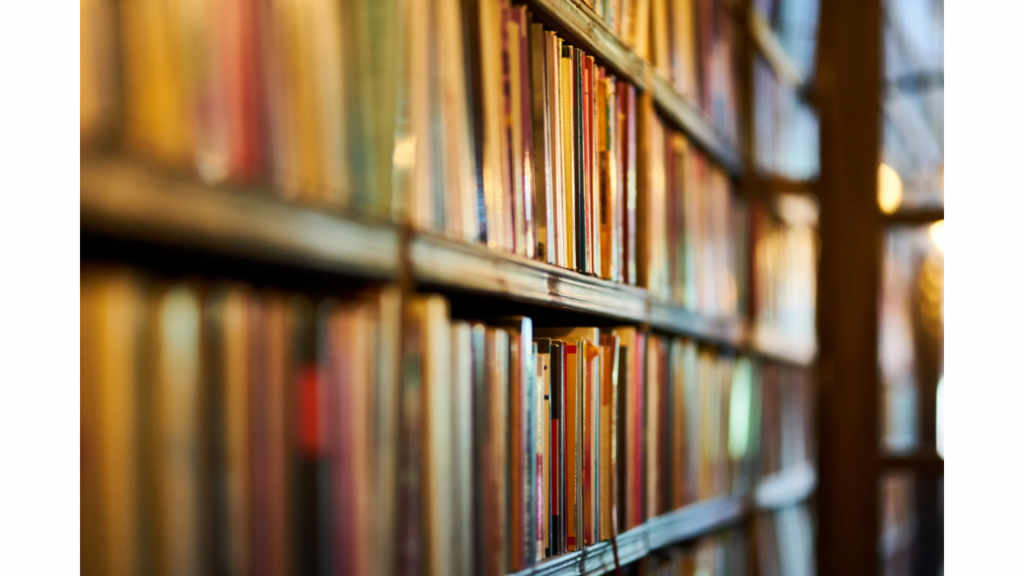
それには、イギリスの歴史が深くかかわっています。
イギリスは今から約2000年ほど前、ローマ帝国に侵略され多くのローマ人が住むようになりました。
その際にブリテン島に住み始めたローマ人は、先住民であるケルト人と戦うために各地に城や砦である「castrum(チェスターの語源)」を建設しました。
つまり、現在地名に残っているチェスター(chester、cester、caster)はラテン系であるローマ語が由来の言葉となります。
ローマ人による支配は3~4世紀程で終わりましたが、その後ゲルマン系であるアングロサクソン人がイギリスに入ってきて住むようになりました。
彼らもまた、戦争のために各地に城や砦である「burg、burh」を建設し、それらが現在のバラやベリーへと変化しました。
このようにして、ラテン語由来であるチェスターとゲルマン語由来であるバラやベリーがイギリス内に混在するようになりました。
語源から英語を学ぶ!
今回紹介したバラやベリーと語源が同じ英単語があるので紹介します。
・borough「行政区、自治町村」
・burglar「不法侵入者」(城に侵入する者から不法侵入者の意味)
これらの単語はbrough、burgh、boroughによく似ていますよね。
このように、burg、burhを語源とする英単語は「お城・砦」を連想する意味を持っています。
漢字のへんやつくりと同じように、英単語も語源を知ることによって英単語の意味を推測することができます。
語源をベースにした「英語の語源大全」「英単語の語源図鑑」という本があるので興味がある方はぜひ読んでみてください。
また、「英語の語源大全」を含む語源に関する英語学習の本を月額980円で読み放題ができるKindle Unlimitedというお得なサービスもあるので、費用を抑えながらたくさんの本を読みたい方はこちらもおすすめです。
Kindle Unlimitedは最初の30日間はお試し期間で料金は無料です!
読みたい本がどのくらい読み放題に入っているのか気になる方や電子書籍の読み心地が気になる方でも、30日間の無料体験期間で使い心地を確認することができるので安心です。
また、いつでも簡単に解約できるので、気軽に試してみてはいかがでしょうか!
まとめ
- ○○バラ/ベリーはゲルマン語系古英語のburg、burh「要塞化された町、砦に囲まれた町」が由来
- ドイツにも同じ意味のburgがある
- チェスターも同じ意味だが、こちらは古ラテン語が由来
「語源や由来を知って何かいいことがあるの?」と思う方もいるかもしれませんが、地名にまつわる語源は、知識として面白いだけでなく、英語圏の文化や歴史を理解するための入口になります。
私たち日本人(中国人も)は漢字を見た時「きへんがつくものは木に関連がある」「さんずいは水に関係している」などと漢字の意味を推測することができますが、英単語にもそれに近いものがあります。
今回紹介したように、イギリスやアメリカの地名には、歴史や言語の影響が色濃く残っています。
こうした背景を知ったうえで英語に触れると、単なる「文字」や「音」ではなく、意味のある情報として英語を理解しやすくなるのが特徴です。
英語学習でも同じで、内容や背景をある程度理解している英語をたくさん聴いたり読んだりする方が、自然と語彙や表現が身についていきます。
そのため最近では、英語を「勉強する」のではなく「インプットする」学習法(イマージョン学習など)が注目されています。
語源の全てを知る必要はありませんが、語源を知ることで英単語が覚えやすくなったり英語に対する理解が深まったりするので、興味がある方はぜひ試してみてはいかがでしょうか!
知識の習得や英会話の勉強にはAudibleがおすすめ!
Audibleは耳を使って”本を聴く”サービスなので、通勤通学などの移動中や家事などの時間を有効活用することができます。
また、小説や参考書の他に『スピードラーニング』のような英語教材、ポッドキャスト、ASMR作品などの音声作品も聴き放題に含まれているので、興味がある方は30日間の無料体験期間を使って試してみてはいかがでしょうか!
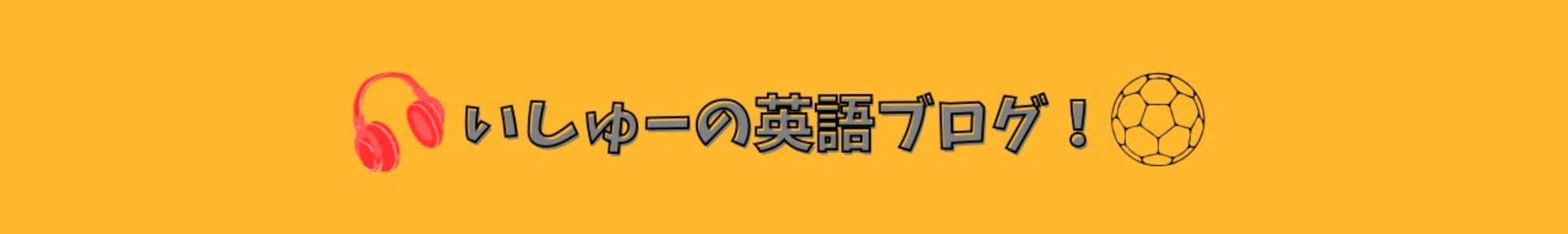
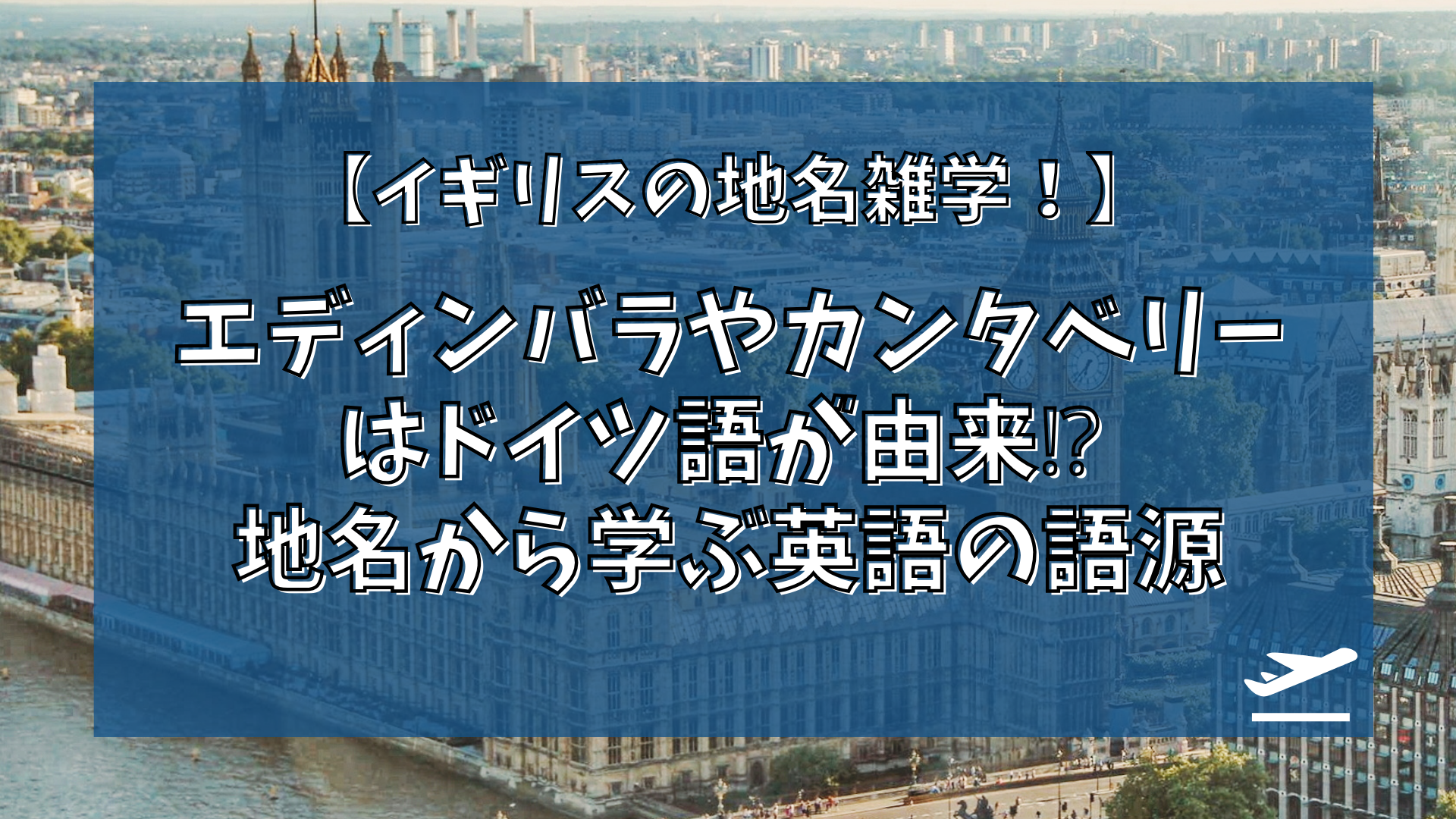

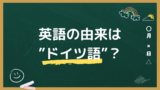
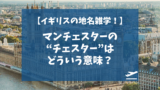

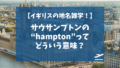
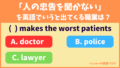
コメント