皆さんはストライキという言葉をご存知でしょうか?
ストライキと聞くと、「海外の交通機関などで従業員が抗議として営業をやめる」といったイメージを持っている方も多いと思います。
このストライキをアルファベットで表記するとstrikeとなりますが、どこかで見たことがありませんか?
そうです。抗議としてのストライキは「打つ、たたく」のstrikeと同じです。
野球やボウリングのストライクと同じですね!
今回は、strikeが抗議としてのストライキとして使われることになった歴史を紹介していきます!
ストライキは帆を降ろすが由来?
strikeには「打つ、たたく、攻撃する」の他に、「(船の)帆を降ろす」という意味を持っています。
実は、抗議を意味するストライキは、この”帆を降ろす”が由来となっています。
ストライキという言葉が生まれたのは、18世紀のイギリスとされています。
当時の物流といえば船であり、シェイクスピアの『ヴェニスの商人』でも資産家が船を所有し貿易で財を成す描写があるなど、船は物流や移動手段として盛んに利用されていました。
しかし、当時の船員たちの労働条件は悪く苦しんでいたため、労働条件の改革や賃金の引上げを求めて船の帆を降ろし(strike)、港の業務を停止させてしまいました。
この事件によりstrikeが労働者の抗議行動や業務の停止を意味するようになりました。
その後19世紀~20世紀になると産業革命がおこり、イギリス全体で従業員たちの過酷な労働環境が問題となり、労働者たちは組合を組織して労働環境の改善や賃金の引き上げを求めてストライキを行うようになりました。
工場の経営者としては生産がストップしてしまうことが一番の痛手であるので、ストライキは経営側と交渉する強力な手段として全世界へと広まり、現在でも使われています。
まとめ
- ストライキは野球やボウリングのストライクと同じstrike
- ストライキは”帆を降ろす”が由来(船員が帆を降ろし港の業務を停止させたことから)
- ストライキは労働者の権利として法で守られている
今回はストライキの意味や由来を紹介しましたが、私たちは意味や由来をしっかりと知らなくても正しく使いこなすことができますよね。
これは、日常生活で大量にインプットをしているからで、自然と正しい用法が身についているためです。
実は、これは英語学習全体にも共通していて、英語表現や英文法、語彙を暗記するよりも意味や文脈をある程度知っている英語(イメージしやすい英語)をたくさんインプットする方が、学習効果が高いと言われています。
そのため最近では英語を「勉強する」のではなく「インプットする」学習法(イマージョン学習など)が注目されています。
文法や単語を一つずつ覚えるよりも、まずは英語に触れる量を増やす方が英語が「わかる感覚」をつかみやすくなるので、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか!
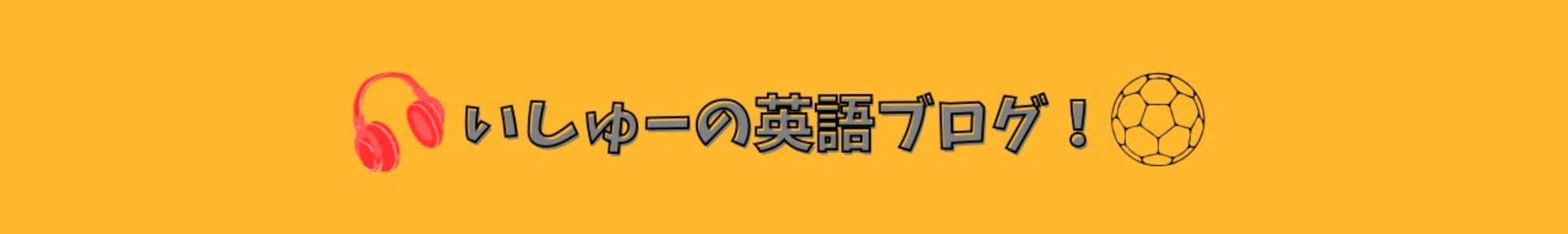
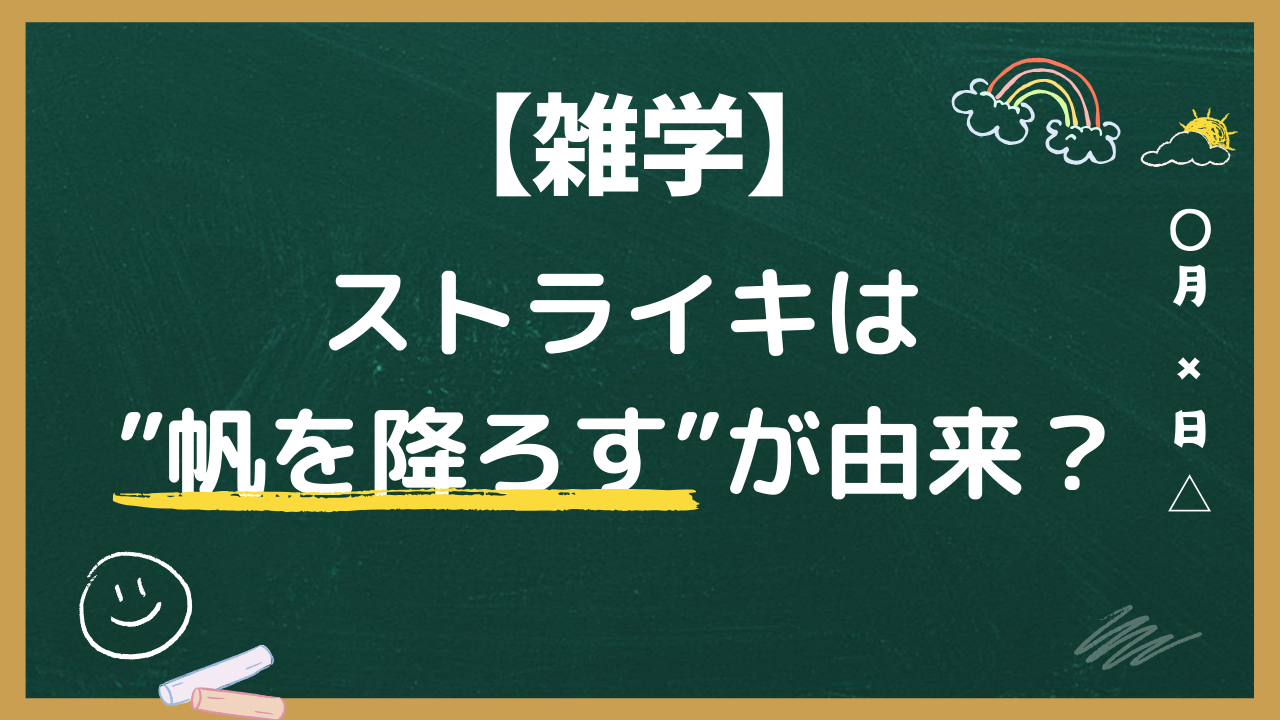
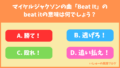
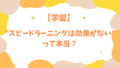
コメント