(この記事にはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイトを含む)が含まれています。)
「手持ちの参考書やプリントをデジタル化して、スマホやタブレットで勉強できたらなあ」
と思ったことはありませんか?
参考書はそれなりにサイズや重量があるので持ち運びできる量に限りがあり、通勤通学などのスキマ時間にバッグから取り出すのは少し面倒ですよね。
近年、電子書籍市場が拡大しているのでスマホやタブレットでも学習できますが、わざわざ同じ本を電子書籍で購入するのは少し気が引けますし、本によっては電子書籍が対応していなかったりします。
そのような方におすすめするのが「スキャナー」です。
スキャナーを使えば、紙の本やノートを電子書籍化して、検索やクラウド保存を活用した効率的な学習が可能になります。
今回は、スキャナーとはどのような機械なのか、また、学習に役立つ機能やメリット・デメリットを詳しく紹介します。
スキャナーとは?
スキャナーとは、紙に印刷された文字や画像を読み取り、パソコンやスマホにデジタルデータとして取り込む機械のことを指します。
書類・写真・本のページなどをスキャンすることでPDFやJPEGなどの形式で保存できるので、いつでもデジタルで閲覧・共有できるようになります。
用途に応じて種類もさまざまで、以下のようなものがあります。
- フラットベッドスキャナー(ガラス面に置いて読み取るタイプ)
- シートフィードスキャナー(複数枚の紙を自動で読み込むタイプ)
- ハンディスキャナー(手でなぞってスキャンするタイプ)
紙を整理して保管スペースを減らしたい人や、参考書やノートをデジタルで持ち歩きたい人にとって、スキャナーはペーパーレス生活を実現するための必須のアイテムになります。
スキャナーを導入するメリット
- 教材の持ち運びが不要
- 検索性が向上する
- スペースが確保できる
- クラウドが便利
- 書き込みやマーカーが自由
教材の持ち運びが不要
参考書やノートをスキャナーで電子化すれば、スマホやタブレット1台で数十冊分の教材を持ち歩けます。
通勤・通学中やカフェでの学習にも便利で、紙の本の重さから解放されます。
また、スマホやタブレットにスタンドを装着することで机のスペースを確保でき、ノートや電子メモパッドが置きやすくなります。紙の参考書の場合、ペンケースや消しゴムを使ってページが勝手にめくれないようにするなど面倒ごとが多いですが、電子化するだけでそのような煩わしさから解放されるのもメリットになります。
検索性が向上する
スキャナーのOCR機能を使うと、スキャンした資料内のテキストをデータ化し、キーワード検索が可能になります。
紙の参考書だと目次や索引から探す必要がありますが、電子化されたPDFなら一瞬で必要なページにたどり着けます。
大量の資料から重要な情報を効率的に抽出できるため、試験対策やリサーチにも非常に役立ちます。
スペースが確保できる
スキャナーで紙の書籍やプリントをデータ化すれば、物理的な保管場所が不要になるので、本棚を占領していた教材や過去のノートを整理でき、部屋がスッキリ片付きます。
さらに、データ化したファイルはクラウドや外部ストレージに保管可能なため、紛失や劣化の心配もなく、長期的に学習教材を安全に管理できます。
クラウドが便利
スキャンしたデータをGoogle DriveやDropboxなどのクラウドサービスにアップロードすれば、パソコン・スマホ・タブレットからいつでもアクセス可能です。
家ではPC、外出先ではスマホといった使い分けができ、環境を選ばず学習を継続できます。
クラウド上に自分だけの「教材ライブラリ」を構築することで、学習の自由度と効率が格段に向上します。
書き込みやマーカーが自由
PDFリーダーアプリを使えば、参考書に直接書き込みやマーカーを引くことができます。
紙とは異なり、マーカーや色付きのペンで書いても「消す・書き直す」ことができるので、自分が使いやすいように参考書をアレンジすることができます。
スキャナーを導入するデメリット
- 初期費用がかかる
- 裁断作業が必要な場合がある
- 作業時間がかかる
- 画質や設定の調整が必要
初期費用がかかる
高性能なスキャナーは1万円〜数万円と、導入コストが必要です。
特に高速スキャンやクラウド連携、OCR機能などを備えたモデルは価格が上がる傾向にあります。
長期的には学習効率を大幅に改善できる投資ではありますが、初めて導入する際にはコスト面がネックになるかもしれません。
しかし、スキャナーを1度導入することで、参考書以外の書籍や仕事や学校の書類の電子化などペーパーレス化を一気に進めることができるので価格以上の恩恵があります。
裁断作業が必要な場合がある
スキャナーを使って書籍をスキャンする際、ページをバラさないとスムーズにスキャンできず、裁断機(カッター)で背表紙を切り離す作業が必要になります。
そのため、本を破損したくない方や本を売りたい方にはスキャナーはあまり向いていません。
本を裁断せずにスキャンできるスキャナーも存在しますが、一般的なスキャナーよりも速度が遅く、大量の本を電子化するのには向いていません。
作業時間がかかる
大量の参考書やノートを電子化する場合、スキャン、OCR処理、ファイル整理など、想像以上に時間がかかることもあります。
特に初めての人は、解像度設定やファイル名の管理に手間取りやすいです。効率化のためには、ADF搭載の高速スキャナーやクラウド自動保存機能を活用すると作業時間を大幅に短縮できます。
画質や設定の調整が必要
スキャン品質を高めるためには、解像度(dpi)の設定やカラー・モノクロの選択などを調整する必要があります。
高解像度でスキャンすると文字はくっきりしますが、データ容量が大きくなり保存先を圧迫する可能性があります。
とはいえ、一般的な用途でのペーパーレス化であればそこまで設定は難しくなく、説明書も付いているのでそこまで気にする必要はありません。
おすすめスキャナー3選!
富士通 PFU ドキュメントスキャナー ScanSnap iX1300
ScanSnap iX1300は、コンパクトながら高速かつ多彩なスキャン機能を備えたモデルです。
本体の上部から給紙する「Uターンスキャン」では、A4カラー両面を毎分30枚(60面)連続スキャン可能で、最大20枚までまとめて処理できます。従来の機種よりも大幅に高速化し、簡単かつ迅速に書類を電子化します。
前面から給紙する「リターンスキャン」では、写真・名刺・プラスチックカード(厚さ2mmまで)など多様な原稿に対応。A4サイズなら5秒で両面読み取りでき、スキャン後は手前側に原稿が戻るため、少量の原稿スキャンにも便利です。
コンパクトなデザインで場所を取らず、Wi-Fi接続や「ScanSnap Cloud」を介したクラウドへの自動保存も可能です。
iOCHOW ドキュメントスキャナー ブックスキャナー S5
このスキャナーは、自動トリミング機能で不要部分を削除し、書籍スキャンモードでは自動平坦化技術により見開きページの湾曲や指の映り込みを補正します。
OCR機能を搭載し、スキャンしたデータをWord・Excel・PDF・TXTへ簡単に変換可能です。また、2200万画素の高解像度で最大A3サイズまで対応し、LEDライト付きで暗所でも鮮明にスキャンできます。
USBケーブル1本でPCと接続して簡単に操作でき、データ転送と電源供給もスムーズにおこなうことができます。
さらにスキャンだけでなくビデオ録画やリアルタイム投影が可能なので、会議やプレゼンなど幅広い用途に活用できます。
重量は約0.8kgとコンパクトで、折り畳み式で持ち運びも便利です。
リコー PFU ドキュメントスキャナー ScanSnap SV600
ScanSnap SV600は非接触で原稿をスキャンでき、新聞や雑誌の見開き、綴じ本、厚みのある原稿(30mm以下)、傷つけたくない絵や写真などもそのままデジタル化可能です。
ページをめくりながら連続スキャンし1つのファイルにまとめられるほか、中央部のゆがみ補正や指の映り込み削除など、書籍スキャン向けの補正機能(ブック補正・ポイントレタッチ機能)が充実しています。
「オーバーヘッド読み取り方式」を採用しているため原稿台が不要で、省スペース設計も魅力です。
また、付属ソフト「ScanSnap Home」により、読み取りからデータ整理、閲覧、編集、検索、アプリ連携までを一元的に管理可能で、学習機能を活かした効率的なデータ運用が可能です。
まとめ
紙の本は数が増えると置くスペースに困りますし、持ち運びする数も限られてしまいます。
その点、スキャナーを活用すれば、参考書・ノート・プリントを電子書籍化でき、本の整理や持ち運びがとても楽になります。
また、最新のスキャナーはスキャンの効率だけでなく、OCR機能やクラウドなど学習に向いている機能が充実しているので紙の参考書よりも使い勝手が良くなります。
紙の参考書やノートをデジタル化して、より快適なペーパーレス生活を送ってみてはいかがでしょうか!
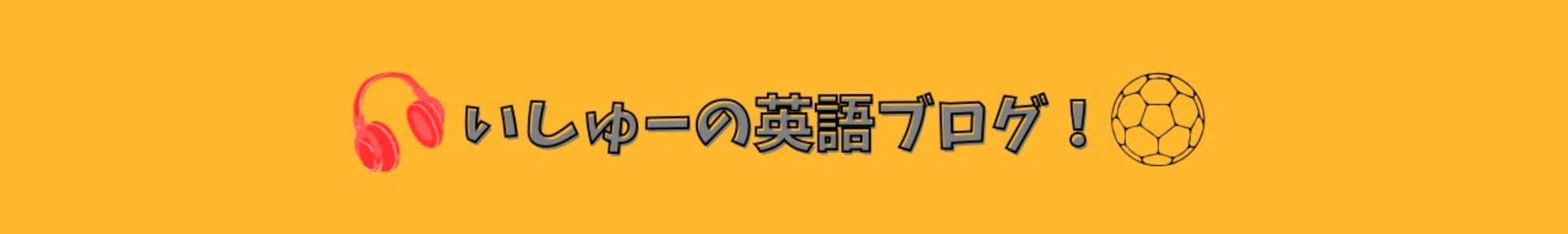



コメント